
〔2018年1月〕
通常よく見る葉牡丹が伸びて、くねくねと伸びた茎の先に葉牡丹がぽこんと付いている状態を「踊り葉牡丹」といいます。
リース型プランターでリースに仕立てた葉牡丹を春に鉢に植え替えて育てました。
超コンパクトな「踊り葉牡丹」を作りたいと育てて1年。11月に入って中心部がほんのり色づきはじめました。冷え込みが足らず日差しが強くて暖かい日が続いていたせいなのか、思ったよりも色づいていませんでしたが、12月に入り徐々に色づいた葉が開きはじめ、お正月を迎えました。
古い緑の葉が落ちて、色づいた新葉が出てきて結果として花のような葉牡丹が出来上がるのですね。思ったよりも葉の数は少ないですが結構いい感じに育ちました。
もっとも、色付いた新葉が展開しもっとも美しく鮮やかになったのは2月に入ってからです。
色付きについては、その年の秋~冬~春の気温によって、色付きの時期や程度が大きく影響します。
それにしても花のように色づく冬、ツリー型に変化する春、花の季節、涼しげな青い葉の夏、葉牡丹は変化を年中楽しめる植物です。
葉の色づきに関わる内容を中心に、この1年の様子や育ててみての注意点などを紹介したいと思います。
なお、以前のリースの記事はこちらです。また、花が咲くまでの記事はこちらです。
この記事後も育てており、現在栽培2年目突入です。育て方については2年の経験に基づいて書いています。
また栽培2年目の寄せ植えの様子はこちらの記事をご覧ください。
葉牡丹の色づきが悪いのはなぜ?
暖かいと色づかない
葉牡丹は寒さに晒されないと色づきません。秋の日差しは結構強くて我が家のベランダも快晴の日には、日中30℃を超える日もたびたびあるくらいです。我が家の葉牡丹も中心部がほんのり赤くなったのも1年目の2017年は11月中旬、2年目の2018年は12月末と思っていたよりずっと遅かったです。
また1度寒くなっても、その後、暖かい日が続くと色づきが止まり、再び緑色に戻ってしまいます。一度緑色に戻れば、もう色づかないとも聞きますので心配ですね。そんなわけで、暖地や暖冬とよばれる年にお家で自然に育てるときれいに発色しないこともあるかと思います。

〔2017.11.29撮影〕
葉牡丹は新葉が色づきます。古い葉もわずかに色が変わりますが、葉全体が美しく発色するのは新葉です。
下の写真の11月6日と12月1日に撮影した写真でアオムシに食べられた葉の位置で比べてみると、出てきた新葉だけが発色していることがわかります。12月に入って、本格的に寒くなり、2018年のお正月には色づいた葉が増えました。



〔11月6日〕〔12月1日〕〔1月2日〕
肥料が多いと発色が悪い
9月頃から置き肥を止め、10月頃から肥料を与えないようにします。窒素分の多い肥料は青々として発色が遅れます。
葉牡丹を育てる上での注意点
春から秋まで害虫に注意
葉牡丹は、アブラナ科の植物なので、キャベツと同様アブラムシやアオムシに気を付けましょう。
アブラムシなどはオルトランなどを早めに対処しておいた方がいいと思います。
ところで、上の11月6日の写真の葉を食べたアオムシです。我が家では春から秋まで全く被害がなかったので、まさか11月になってアオムシに食べられると思っていなかったのでうかつでした。


特に柔らかい新葉を食べるので、気が付いた時には結構な被害になっています。上の写真の葉牡丹は色づき始めた新しい芽葉を全部やられました。今現在新しく発色した葉が出てきていますが花のような形に整うには時間がかかりそうです。ご注意を!
育てる環境
夏の直射日光は避けますが、一年中日当たりの良い場所で育てます。
水やりの仕方
鉢植えでの水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりとあげます。夏は朝夕、冬は数日に一度、それ以外の季節は1日~2日に一度くらいのペースになると思います。乾燥を好むので、土が湿っている間は水やりしないように気をつけましょう。
肥料のあげ方
肥料もあまり必要ありません。10月から翌年3月くらいまでは肥料を与えません。春から夏は置き肥を与えます。我が家では5月の植え替え時に元肥入りの培養土に植え替えし、7月初めに置き肥をしました。置き肥は大体2ヶ月効き目があります。9月は2回ほど液肥をやり、10月からは何も与えていません。
我が家の1年を通した育て方記録
12月
ポット苗を購入してリースに仕立てました。

2月
随分生長して華やかです。高さが出てきたので吊らずに置いて育てています。水やりは、土の乾き具合を見てリース型プランターにかけてやってます。


4月
菜の花に似た花が咲きます。

リース型プランターにはわずかな土の他は水苔とヤシマットだけで植え付けているので、保水性があまりありません。乾燥を好む葉牡丹にはちょうどよいのですが、春になり、土が乾くのか早くなりました。水苔は一度乾くと水を吸収しずらくなるので、水苔や土の状態を見て、数日に一度プランターごと水に浸けるようにしています。リース型プランターはわりと大きいので、レジ袋やごみ袋を利用するといいですよ。

茎の切り戻し

4月上旬、花が咲くと葉牡丹を切り戻します。葉の間に芽が見えるので芽を残して切ります。切った先端の脇芽が育つので、切る位置はお好みの高さです。うちでは、葉を数枚残した割と根元に近い位置でカットしました。


4月の中旬頃にカットして、5月の初旬には、脇芽が下の写真くらいに育ちます。

この脇芽がすくすく育ってもう一度花をつける株もあります。その場合は、花をもう一度摘みます。
また、5月になると真夏日も出てきます。ワイヤーリースでは乾燥しすぎるため鉢に植え替えました。元気のよい株だけを残して、まとめます。一本ずつ別の鉢で栽培するほうがそれぞれの株にとって良いと思いますが、やはりスペース的な問題もあるし、小さな葉牡丹がたくさんつく姿をイメージして作りました。
7月

和風な青い鉢と白い石で涼し気にしています。葉も青みを帯びているのでよく合っているの思います。葉牡丹は色づいている時しか価値がないように思っていましたが、案外一年中楽しめる植物ですね。茎の葉のとれた後の模様も面白いです。高低差もついていい感じです。

9月
9月に入ると置き肥を止めます。
11月
下のほうの葉が徐々に落ちていきます。それと同時に新葉が色づき始めます。

〔2017.11.6撮影〕
12月

〔2017.11.27撮影〕
12月になり、ぐっと寒くなりました。
お正月
明るく可愛らしい踊り葉牡丹になりました。

〔2018.01.02撮影〕
2月
もっとも美しくなったのは2月~3月頃です。色付き始めから約3か月ですね。

〔2018.02.16撮影〕
3月

〔2018.03.13撮影〕

3月の中旬になるとつぼみが出始めました。春ですねぇ。
ここから2年目になります。育て方は繰り返しです。2年目からの葉牡丹の様子はこちらの記事を見てください。
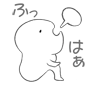

コメント