〔2023.12.09〕
エアプランツをコルク板に寄せ植えして5年と少し。とっても小さかったイオナンタが大きく生長し、11月下旬に小さい方のイオナンタに、12月初旬に大きい方のイオナンタに花が付きました。長かった~。詳しくはこちらをご覧ください。尚、2つは百均で入手したもので、共にイオナンタですが葉の雰囲気が少し違うので種類が違うと思われます。



〔2018年7月〕
寄せ植えを作った頃の写真です。

バージンコルク板にエアプランツをレイアウトしています。特徴的な花苞がついたファシクラータをメインに、イオナンタやハリシー、ベルティナを寄せ植えしています。どれも百均やホームセンターで入手できるお手頃価格のエアプランツです。
4年経ち、途中大きくなるにしたがって、ベルティナを外し、ファシクラータ・イオナンタ・ハリシーで仕立て直して、現在に至ります。
我が家の寄せ植えの方法や生長の様子をご紹介します。
尚、ベルティナについて別記事があります。開花から子株形成までの記事がこちらございますのでよろしければ見てください。
エアプランツ(チランジア)を寄せ植えする
ガーデニングショップで、花苞が出ているファシクラータを見つけて購入、家にあったバージンコルクの板に着生させることにしました。

で、レイアウトを考えだしまして。どんなふうに作ろうかとか頭でイメージしていきます。こういう一連の作業が一番楽しいですね。
以前から育てていたベルティナも入れることにします。ベルティナは一年前にホームセンターで花が咲く直前のものを購入しました。無事花が咲き、子株ができて、今では子株の方が大きく育った状態です。
バージンコルクを縦にしてレイアウトを考えていたのですが、ファシクラータが割と大きいので、バージンコルクの下側に配置すると収まりが良いです。色々と考えていると、上の方に小型のエアープランツを付けたくなったので、イオナンタとハリシーを百均で入手してきました。
エアプランツの寄せ植えは、見映えもいいですし、育て方が同じものを寄せ植えすると日ごろの管理が楽になりますよ。
レイアウトのコツ
これはお好みにもよると思いますが、このようなことを考えて配置しました。
- 葉の特徴や大きさが違うものを寄せ植えする
- 配置に流れやリズムを感じさせる
- 抜けの部分(空間)を作る
- 花茎や花苞が付いた時のことをイメージする
- 着生素材の凹凸や特徴を活かす
といったことでしょうか。
チランジアは大きくトリコームに覆われている銀葉種とトリコームの少ない緑葉種があります。銀葉種の方がトリコームに覆われているので太陽の光に強く、水を好む傾向にあるようですが、どちらの種類も寄せ植えできないほど管理する場所や水やり方法が異なるわけでもありません。経験的にですが寄せ植えして同じお手入れでほぼ問題はありません。
レイアウトについては、花茎は長く伸びるタイプなのかそうでないのかといったことや、子株が形成されたとき空間的余裕があるのかなど、生長した姿をイメージして空間的バランスを考えて、寄せ植えするエアープランツを選び、配置するとよいと思います。そして、着生素材(バージンコルクを例に挙げると)のくぼみなどにエアープランツの株の根っこ部分が入るようにすると固定もしやすいし見た目も自然です。

エアプランツの固定に何を使うか… 接着剤?針金?
植物なのに…と抵抗を感じられる方も多いと思いますが、小型のものは接着剤を使って短時間で固定するのが、最もエアプランツを傷つけない方法だと思います。というのも、小型のものを針金で固定しようとすると、位置を少しずらしたり角度を調整したりとエアープランツに触れている時間が長くなりますよね。その間に葉が折れたり、トリコームがはがれたりしてしまうのです。
接着剤は、水に強くて速乾性のものを使いましょう。あまり難しく考えず、どこでも売っている速乾性多用途ボンドや瞬間接着剤で大丈夫です。瞬間接着剤はゼリー状のものが使いやすいです。グルーガンでの接着については、あくまで経験としてですが、ポロッと取れやすいですし、量もべったりつけないと固定できないのではないでしょうか。
また接着剤を使う場合、エアプランツの根が生える部分全体を接着剤でべったり覆ってしまうのは避けましょう。エアプランツの向きや固定する部分をあらかじめ考えておいて、スポット的に接着剤を置いて固定します。うちではエアプランツの根が生える部分を外して3か所くらいゼリー状の瞬間接着剤を点で置き、貼り付ける素材にやんわり押しつけて留めています。大きなものは、針金と接着剤を併用すると固定しやすいです。針金を使う場合もバージンコルクなら千枚通しでも簡単に穴が開けられます。



ミズゴケで根の周りを覆う
チランジア類は、根が生える部分が若干湿っているほうが発根しやすかったり、成長が順調だったりします。なので、エアプランツを固定した後は、隙間をミズゴケで覆うといいです。小さいエアプランツなら長いミズゴケ一本をエアプランツの根元にに巻き付け竹串などでエアプランツと板との隙間に押し込みます。バージンコルクのくぼみにエアプランツを固定するとこの作業はとても簡単で見た目も自然でいいです。


ファシクラータも購入後、そのまま水やりをしていた2週間はなにも動きがありませんでしたが、バージンコルクに固定して根廻にミズゴケで埋めてすぐに花が出てきました。たまたまかもしれないですが、あまりにもタイミングが良かったです。その後順調に毎日ひとつづつ花を咲かせました。
ハンギングのコツ
うちでは、屋内は壁にピクチャーレールを取り付けているので、そこから壁際にハンギングします。
以前、ビカクシダ・リドレイをバージンコルクに着生させたときは、ハンギング用にバージンコルクの裏側にネジを2本刺し、ワイヤーをかけてハンギングできるようにしました。

このやり方は、リドレイの生長に伴い重量が増えても耐えられるようにと考えました。
今回のエアプランツは生長しても重量が軽い状態を維持できそうなので、バージンコルクの厚みを利用して、ネジフックを使いました。ピクチャーレールから吊り下げるワイヤーの壁からの距離や、レイアウト済みのバージンコルクの重量バランスを考えて、ネジフックの取り付け位置を決めます。

バージンコルクには、もろい部分もありますのでよく確認してくださいね。取り付ける際は、ただねじ込むのではなく、接着剤を併用するとしっかりとまりますよ。

実際に吊ってみるとこんな感じです。

チランジア類のエアプランツの育て方
チランジアの仲間はとても多く、中には難しい種類もあるかもしれませんが、比較的安価で購入できるものは、育て方もコツをつかめは簡単です。必要なのは、適度な日照と風通しです。温度が低くなる冬場は、室内の陽が差し込む明るい窓際などで育てますが、春~夏~秋は屋外の風通しのよい明るめの日陰で育てるといいですね。
エアプランツの水やり
よく、『エアプランツは空中の水分を葉から取り込んで生長するので、頻繁な水やりは必要ない。』ですとか、『週に1~2回霧吹きで水をかけてやる程度でいい。葉の根元に水が溜まったままになると腐ってしまう。』とかいいますよね。
うちで実際に育ててみて思うのは、確かに冬場の寒い時期に室内で管理するときに水やり加減に気を遣う必要はありますが、春~夏~秋の季節、屋外で育てると案外、普通の植物と同じように水やりしても大丈夫で、簡単に育てられます。エアプランツだから水やりしない、とか区別はしていません。
ベランダで育てているときのうちの水やりは、じょうろでバシャバシャと水をかけるだけです。水やりのタイミングは気温が穏やかな早朝か夕方がいいです。一日一回なら夕方ですね。風通しがいい場所では、多少葉の根元に水が溜まっても大丈夫ですが、心配ならエアプランツを逆さにしたり、パッパッと振って根元の水を切っておいたら安心です。
我が家ではベランダで色々な種類の植物を育てていますが、水やりのタイミングはみな同じにしています。また、日ごろの管理が同じものを選えで寄せ植えにすると、こういうところが楽ですよね。

冬場の室内環境での水やりは、ともかく葉の根元に水が溜まらない様、よく水を切ることです。水やりの頻度は室内環境で違いますので、様子を見て水やりします。
霧吹きを使うのも手軽でいいですね。我が家は『マイクロンスプレー』を使っています。この霧吹きは、霧が細かく、連続してでます。どの植物にも重宝しています。
 | マイクロンスプレー ワインレッド 250ml ミスト スプレー【HLS_DU】 関東当日便 価格:526円 |
肥料やり
肥料は、真夏と冬場を避け、春秋に液体肥料をサボテンに肥料やりするのと同じ濃度に薄めて、2週間に1度くらいの割合で与えています。与え方は、霧吹きでもじょうろでも、水に浸ける方法でも大丈夫ですが、葉に余分な薬剤が残ってしまうとよくないので、一度乾いたあたりで、もう一度水で流しています。
葉に直接スプレーするタイプの活力液も時々使っています。目に見えて効果的ということはないのですが、順調に旺盛に育っているので、有効だと思っています。エアプランツは、特に葉から水分を吸収するので、スプレータイプは適しているのではないでしょうか。ハイポネックスもフローラHB-101もどちらも使いやすくいい感じですね。
エアプランツを固定する素材は何がいいか
エアプランツの飾り方はインテリアとしてはいろいろありますね。しかし植物なので、水やりもできて、屋外にも出したりといったことを考えると、固定するとすれば流木やコルク板、網、植えこむ場合は鉢に軽石とバークといったところでしょうか。
我が家では着生させる素材としてバージンコルクをよく使います。今回使っているバージンコルクは、通販で大きめサイズを購入して、ビカクシダ・リドレイの板付けに使用したときの残りです。バージンコルクとはコルクガシの樹皮のことです。見かけもワイルドでビジュアル的に好きなのですが、機能的な面でも、エアプランツやビカクシダなどを固定する素材としていい素材だと思います。我が家が思うバージンコルクのいい点は、下に記したような点です。
バージンコルクを使うメリット
- 水切れが良い
水をはじくいてすぐに乾くので、水やりから壁に取り付けるまで短時間ですみます。流木だと乾くの時間かかりますよね。部屋の壁を濡らして壁にシミやカビが生えたらいやですよね。バージンコルクは、そういったトラブルが起こりにくい素材です。また、水をはじきますが自然素材なので、バランスよく適温・適湿を保ってくれます。植物にとっていい感じの素材です。 - 根が張りやすい
バージンコルクは自然に凹凸があるので、エアプランツを固定しやすいし、根が張りやすいです。コルク板のくぼみを利用して固定すれば、簡単に取り付けられます。ごつごつと凸凹があるほうが植物は根を張りやすいのです。 - 軽い
ハンギングするときに軽いほうが安心ですね。万が一落下しても家具や床を傷つけにくいです。 - 加工しやすい
柔らかいので穴を空けたり削ったりと加工がしやすいです。結構分厚い部分でも、電動ドリルなんて使わずにキリを使って比較的容易に穴を空けられます。
バージンコルクを使うデメリット
- もろいところがある
バージンコルクは多孔質なので強度的には強くありません。また、コルク板の場所によって強度が変わるのでハンギング用のフックなどを差し込む場合は注意が必要です。また、着生させた植物の重量などを考えてハンギングの仕方も考える必要があります。
デメリットもありますが、うちではメリットの方を多く感じるので、バージンコルクを良く使うようにしています。
通販なら入手しやすい
バージンコルクは、ホームセンターやガーデニングショップなど探してみても、置いているところなかなか少ないです。置いてあっても少量で必要な大きさを選べなかったりするので、やはり通販が便利です。形は選べませんが、大きめのものを購入して好みの形に加工するといいですよ。加工は簡単にできます。また縦横の寸法をよく確かめて購入してくださいね。だいたいの寸法しか書いていないので、納得の上購入してください。うちで購入したのは以下のバージンコルクです。
 | バージンコルク フラット1個 大(サイズ・形のバラつきあります) 価格:3801円 |
開花の様子
バージンコルクに寄せ植えしたファシクラータは、順調に生長しています。2018/07/21現在で、5つ目の花が咲きました。
〔2018.07.13〕

〔2018.07.21〕

室内でのハンギング

ビカクシダのリドレイやアルシコルネとともに壁面に掛けた写真です。絵画とのマッチングもよく、劣らずアーティスティックです。植物のハンギング、凝りだすと癖になりますね。
1年後の生長の様子
〔2019.08.05〕
あっという間に一年経ちました。日ごろ気づかないうちにエアプランツたちも発根してしっかり生長していました。


向かって右上角のイオナンタは、なにかと邪魔で擦れたりして傷ついてしまうのでとってしまいました。残り2つ、りっぱに大きくなってます。


ハリシー2つ、葉の広がり方に差が出てますが、どちらも元気です。


ファシクラータは、花後に子株が生長しました。そろそろ親株を切り離します。


ベルティナは半年ほど前に親株が衰えてきたので切り離しました。子株育っています。
メンテナンス
一年経って、ミズゴケを増量したり、ファシクラータの株分けしたりとメンテナンスしました。
ファシクラータは、一度コルク板から外し、親株から子株を手で取り外しました。新しい根が出ていたので根を包むようにミズゴケを巻いて、元の針金で留め直しました。
全体はこんな感じです。

花が咲くのはまだまだ先のようですが、みんな大きくなりました。涼し気でいい感じです。
3年後の生長の様子
〔2021.04.21〕

3年の間に、それぞれ大きくなってきたので、レイアウトを見直しました。具体的には、ベルティナを外して、ハリシーの配置換えをしました。みんな大きくなりましたー。イオナンタは2種は、3年前は同じような大きさだったのに、種類の違いが歴然としました。大きさや葉の太さが違いますね。なんという種類か同定できないのですが、大きいイオナンタは、とってもポピュラーな品種だと思います。一番上についている小さめのイオナンタは、まぁ、イオナンタの細葉タイプというようにしてます。
最近になって、イオナンタ両方ともに葉先が赤くなってきました。ひょっとしたら花が付くのかな…。様子見ですね。


ハリシーも大きくなりました。

蕾がつくか様子見していたんですが、ただの日焼けでした。
4年後の生長の様子
〔2022.05.28〕

大きなイオナンタは、自重で下を向いてきたので、上向きになるようにコルクの小片を株の底部分に挟みました。着生しているのですが、根とコルク板の隙間を見つけて、コルクを小さく砕いたものを挟み込み、コルク板とコルク小片を接着剤で固定しました。
みんな大きくなっています。


5年後の生長の様子
〔2023.11.26〕
2つあるイオナンタの一つが開花しました。葉があまり赤くならなかったので、なかなか気づきませんでした。毎年いつ咲くのかと思っていましたが、やっと開花が見られました。時間がかかりましたが、感慨深いですね。

数日花を楽しみ萎れてきたら、花は根元から摘み取ります。花を咲かせるのはかなりエネルギーを使うので、出来るだけ早く摘み取ったほうが体力が回復しやすいです。また、その個体からもう花が咲くことはなく子株を形成します。また時間をかけて生長していくことでしょう。
それにしても、もう一つのイオナンタはいつ咲くのでしょうね。かなり大きくなってます。イオナンタでも今回咲いたのと種類が違うようです。葉の感じが2つ比べると違いますよね。ただ、どちらも購入時の名称はイオナンタなんで、同定はできませんが…。

全体は、こんな感じになっています。大きい方のイオナンタは、大きすぎて、たびたび自重で下を向いてくるので、気になるようになったら、テグスなどで直しています。レイアウトも間延びしてきたので、そろそろ寄せ植えを見直ししようかなと思っています。

〔2023.12.09〕
大きい方のイオナンタにも花が付きました。小さい方が11月下旬に咲いて、大きい方はいつ咲くのやらと思っていたら、案外すぐでした。葉も赤く染まりとても綺麗です。咲き終わった方のイオナンタの葉も開花中のイオナンタより赤くなっています。


見事に咲いてくれたことが嬉しい反面、終わってしまう寂しさもありますね。長い時間かけて大きくなりましたから…。


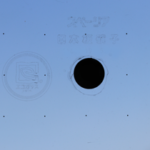
コメント